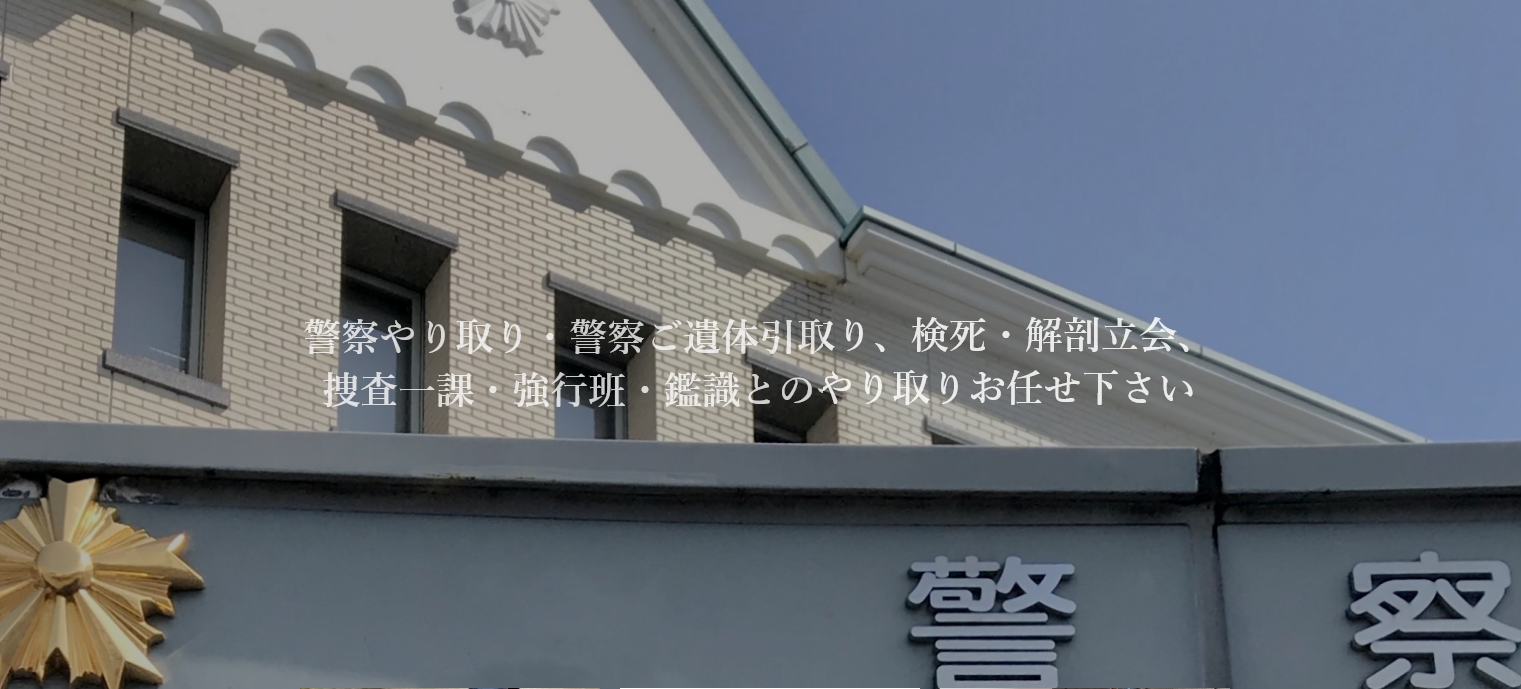
【お断り】 本記事は、交通事故から葬儀ご依頼までの一般的な流れを分かりやすくお伝えするための創作(ドラマ仕立て)です。 警察署での対応、手続きの順序、所要時間などは、地域や事故の状況により実際とは異なる場合があります。あくまで一例としてお読みください。
第1章:予兆のない着信
火曜日の夜だった。 窓を叩く雨音が、妙に耳につく夜だった。
リビングのテレビからは、芸人たちの笑い声と派手なテロップが流れている。僕はソファに深く身を沈め、なんとなくスマホの画面をスクロールしていた。「明日のプレゼン、資料の手直しが必要かな……」。頭の片隅で仕事のことを考えながら、缶ビールの残りを飲み干したとき、ローテーブルの上でスマホが震えた。
画面には「知らない番号」の文字。
嫌な予感がした。普段なら無視するはずのその着信に、なぜか指が伸びた。
「はい、もしもし」 「夜分遅くに恐れ入ります。〇〇警察署、交通課の〇〇と申しますが、〇〇さんの携帯電話で間違いありませんか?」
警察。交通課。 心臓がドクリと大きく跳ねた。
「はい、そうですが……」 「〇〇さん、落ち着いて聞いてください。実は先ほど、お父様の〇〇さんが交通事故に遭われました」
父が? 定年退職後、趣味のカメラを持って夜の散歩に出かけるのが父の日課だった。今日も「ちょっと雨の街を撮ってくる」と言って出ていったはずだ。
「父は……父は無事なんですか?」
受話器の向こうで、一瞬の間があった。その沈黙が、言葉よりも雄弁に絶望を物語っていた。
「残念ながら……搬送先の病院で死亡が確認されました。至急、署のほうへ来ていただけますか?」
「死亡」という二文字が、頭の中で反響する。 嘘だろ。 あの元気な親父が。さっきまで「傘持っていけよ」なんて言い合っていた親父が。
「母には……母には連絡しましたか?」 「いえ、ご自宅の電話が繋がらなかったため、履歴にあった息子さんの携帯にご連絡しました」 「わかりました。すぐ……すぐ行きます」
電話を切った後、僕はしばらく動けなかった。手の中のスマホが、鉛のように重かった。
第2章:長い廊下、冷たい部屋
母を実家でピックアップし、僕の車で警察署へと向かった。 車内は異様なほど静かだった。母は助手席で、ただひたすらに震えていた。「嘘よね、間違いよね」と、うわ言のように繰り返している。ワイパーが雨を弾く音が、メトロノームのように僕たちの焦燥感を刻んでいた。
警察署の夜間受付は、無機質で白々しい蛍光灯に照らされていた。 消毒液と古びた書類の混ざったような、独特の匂いが鼻をつく。
「〇〇さん、こちらへ」
案内されたのは、署の奥にある霊安室だった。 ドラマでしか見たことのない、ステンレスの台が並ぶ寒い部屋。その中央に、白い布をかけられた何かが横たわっている。
「心の準備はよろしいですか」
若い警官が、申し訳なさそうに布の端を掴んだ。母が僕の腕を強く掴む。爪が食い込む痛みが、これが夢ではないことを教えていた。
布がめくられる。
そこには、眠っているような父の顔があった。 ただ、額には白いガーゼが当てられ、少し青白く、そして決定的に「生気」がなかった。
「あぁ……あなた!」
母が崩れ落ちる。その叫び声が、コンクリートの壁に反響して耳に突き刺さった。 僕は涙が出るよりも先に、ただ呆然と立ち尽くしていた。本当に死んだのか? まだ温かいんじゃないか? 今にも「なんだ、大騒ぎして」と目を開くんじゃないか?
だが、父の胸は動かなかった。
第3章:事務的な「死」の手続き
悲しみに浸る時間は、残酷なほど短かった。 霊安室を出てすぐ、別室で事情聴取が始まった。
「事故の状況ですが、信号のない横断歩道で、前方不注意のトラックに……」 「運転手は現行犯逮捕されていますが……」
警察官の説明は丁寧だったが、どこか遠い国の出来事のように聞こえた。加害者の名前、事故現場の図面、目撃者の証言。それらが羅列されるたび、父の死が「事実」として固定されていく。
「それでですね、〇〇さん」
一通りの説明が終わった後、年配の刑事がいかにも言いづらそうに切り出した。
「今回は交通事故、つまり『異状死』という扱いになります。死因を法的に確定させるために、検視、場合によっては司法解剖が必要になる可能性があります」
「解剖……ですか?」 母が怯えたような声を上げる。「夫の体を、切るんですか?」
「正確な死因を特定し、加害者の責任を問うためにも必要な証拠保全なのです。ご遺族には辛いかと思いますが、ご協力をお願いしたい」
拒否権などないようなものだった。 僕たちは同意書にサインをした。ペンを持つ手が震えて、自分の名前すらまともに書けなかった。
「解剖は明日の午前中に行います。その後、ご遺体をお返しできるのは明日の午後以降になる見込みです」
刑事が事務的に告げる。 そして、次に放たれた言葉が、僕たちを更なる混乱へと突き落とした。
第4章:誰も教えてくれない「その後」
「そこでご遺族の方にお願いがあります」 刑事は手元の手帳を見ながら言った。
「解剖が終わりましたら、速やかにご遺体を引き取っていただく必要があります。警察署には遺体を長く安置しておく場所がありません。ですので、明日のお昼頃までに、搬送を依頼する葬儀社を決めておいてください」
「えっ……」
僕は思わず聞き返した。 「葬儀社、ですか? 今すぐに?」
「はい。解剖が終わる時間に合わせて、寝台車で迎えに来てもらわないといけません。お心当たりはありますか?」
心当たりなんて、あるわけがなかった。 父はまだ60代。葬式の準備なんて何一つしていない。互助会にも入っていない。
「あ、あの、警察の方でどこか紹介してくれないんですか?」
すがるような思いで尋ねたが、刑事は首を横に振った。
「警察は民事不介入の原則がありまして、特定の業者を紹介することは癒着につながるため禁じられているんです。ご自身で探して手配していただくしかありません」
突き放された気がした。 父が死んだばかりだ。母は泣き崩れている。僕はパニック状態だ。 それなのに、「今すぐ遺体の引き取り先を探せ」だって?
「とりあえず、今日は一度ご帰宅されて、準備を整えてください」
警察署を出たのは、深夜2時を回っていた。 雨はまだ降り続いている。
第5章:真夜中の迷走
実家のリビングに戻った僕たちは、重苦しい沈黙の中にいた。 母は疲れ果ててソファで眠ってしまったが、時折うなされている。
僕はダイニングテーブルに座り、スマホを握りしめていた。 「葬儀社 おすすめ」「交通事故 葬儀」「深夜 対応」 検索窓に言葉を打ち込むたび、画面には無数の広告が表示される。
『格安プラン!追加料金なし!』 『創業100年の信頼と実績』 『お客様満足度No.1』
どれもこれも、今の僕にはただのノイズにしか見えなかった。 値段が安いのがいいのか? でも安すぎると父に申し訳ない気がする。 かといって、高額な請求をされたらどうしよう。 そもそも、明日のお昼までに迎えに来てくれるところなんてあるのか?
「どうすればいいんだよ……親父……」
誰もいないキッチンに向かって呟く。 答えは返ってこない。
もし適当な業者を選んで、変な対応をされたら? 一生に一度の父の最期を、台無しにしてしまったら? 不安が黒い霧のように心の中を覆い尽くしていく。
スマホのバッテリー残量が減っていく。時間だけが無情に過ぎていく。 明日の朝には、警察に連絡を入れなければならない。
「誰か……誰か、信頼できるところを知らないか……」
頭を抱え、絶望的な気持ちで電話帳をスクロールしていた…
【解説】突然の出来事で「頭が真っ白」になった時、なぜ村岡葬研葬儀社が選ばれるのか
先ほどのストーリーはフィクションですが、そこで描かれた「警察からの突然の連絡」「事務的な対応への戸惑い」「時間制限のある中での葬儀社選び」は、決してドラマの中だけの話ではありません。
突然の交通事故や予期せぬお別れは、ある日突然、誰の身にも起こり得ることです。
そんな極限状態で、私たち「村岡葬研葬儀社」がご遺族のために何ができるのか。なぜ、多くの方に「村岡葬研葬儀社さんにお任せしてよかった」と言っていただけるのか。その理由を、少しだけお話しさせてください。
 |
1. 深夜でも早朝でも、「生身の人間」が寄り添います |
|---|
 |
2. 「警察署対応」という特殊な現場を知り尽くしています |
|---|
 |
3. 「きれいなお顔」でお別れするために |
|---|
 |
4. 「お任せ」と言える安心感を |
|---|
「村岡葬研葬儀社にお任せください」
この言葉は、単なる業務の請負ではありません。「あなたの悲しみを、私たちが一緒に背負います」という約束です。
もしもの時は、迷わず私たちにご連絡ください。 あなたの「どうしよう」を、「よかった」に変えるために、私たちはここにいます。




